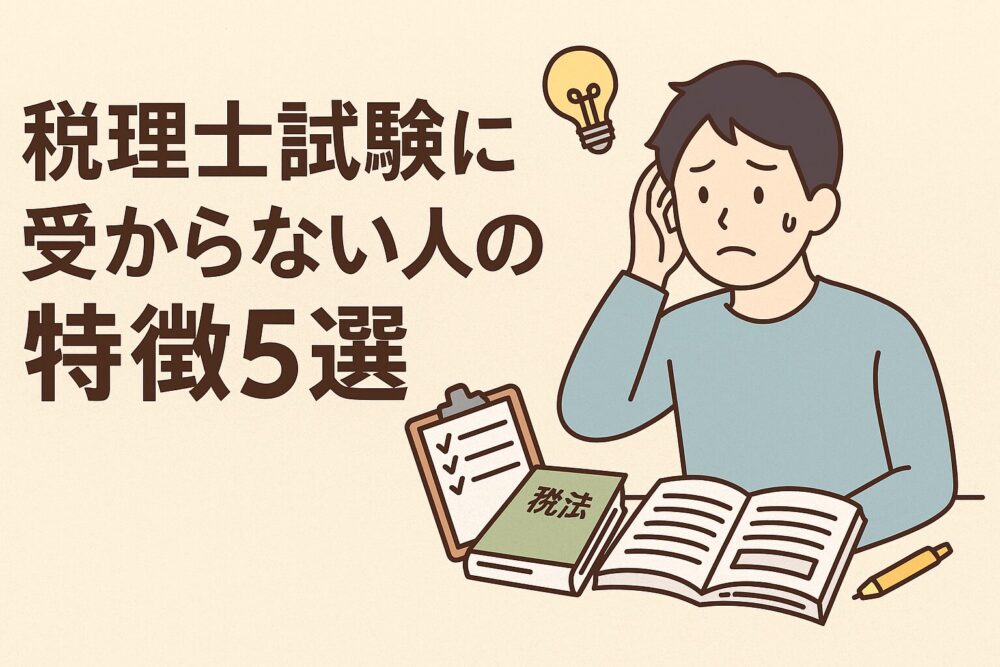「勉強しているのに税理士試験に受からない…」
そう悩む受験生は少なくありません。
税理士試験は“正しいやり方で努力を積み重ねた人”ほど合格に近づく試験。
しかし多くの受験生が、知らないうちに「落ちやすい行動パターン」にハマってしまっています。
この記事では、筆者が10年間で見てきた税理士試験に受からない人の特徴5選をわかりやすくまとめ、合格するために見直すべきポイントまで具体的に解説します。
一つでも当てはまる部分があれば、そこを改善するだけで合格率は確実に上がります。

まずは「落ちる理由」を知り、今日から改善していきましょう。
税理士試験に受からない人の特徴5選

筆者は10年間で、色々な受験生を見てきました。
その中で「税理士試験に受からない人」に共通する特徴は、以下のとおり。
税理士試験に受からない人の特徴①:効率的な勉強方法が身についていない

独学している
税理士試験の最も効率的な勉強方法は、専門学校に行くこと。
今はスタディングなど、格安の講座があるため独学する理由はありません。

そもそも相対試験の税理士試験では、他の受験生と同じく専門学校で勉強するのが最低条件。
相対試験とは?
「他人との比較」で決まる試験。税理士試験の場合は上位10〜20%が合格する。
インプットばかりでアウトプットが足りない
テキストを読むだけの学習は進んでいるように見えても、理解が定着しません。
税理士試験では、理論暗記と問題演習(アウトプット)中心の学習が合格のカギです。

理論を暗記するのは大前提。
暗記方法に悩んでいるなら、以下の理論暗記の記事を参考にしてください。
理解より“丸暗記”に頼ってしまう
丸暗記は応用問題で通用しません。
概念や根拠を理解しながら学ぶことで、初見問題にも対応しやすくなります。

理論や公式を暗記するだけではダメ。
近年の本試験では、事例理論・応用理論がメイン。
暗記した知識を使えるかどうかが合格の鍵です。
応用理論とは?
複数の論点にまたがって記述する理論の問題形式。1つの論点の場合は個別理論という。
事例理論とは?
「実際にこうゆう取引がありました、どうなりますか?」と出題される。結論と根拠規定が求められる
細かい論点にこだわり過ぎる
税理士試験の合格に必要なのは「基本論点を全て取りきること」
出題頻度の低い論点や超難問にこだわるのは間違いです。

ひたすら専門学校に言われたことをやるだけ。
特別なことをやる必要はありません。
復習や間違い分析の仕組みがない
復習の優先順位がつけられず、同じミスを繰り返す人も多いです。
間違いノートや弱点管理表を使うと改善しやすくなります。

社会人の場合は、持ち運びのために間違いノートを作るべき。
筆者は専念してからは、iPhoneのメモアプリに間違いをメモしてました。
税理士試験に受からない人の特徴②:モチベーションが続かず挫折しやすい

目的・ゴール設定が曖昧
「なんとなく資格がほしい」という動機では、挫折しやすくなります。

絶対に税理士になって人生逆転してやる!
税理士試験に合格するには、そんな強い気持ちが必要です。
短期的な結果ばかり見て落ち込みやすい
税理士試験は長期戦。
1〜2か月の結果で一喜一憂すると、学習の安定感が失われます。

点数が伸びない、上位に入れない。
そんな時は何度もありました。それでも諦めずに続けるしかありません。
大切なのは、継続することです。
勉強習慣が“気まぐれ”で安定しない
毎日同じ時間に勉強していない人は、習慣が定着しにくく勉強のリズムが乱れがちです。

働きながらの場合は、早起きして朝勉するのがおすすめ。
夜は残業や飲み会などで、勉強習慣が不安定になりがち。
朝型にすることで、毎日安定して勉強できます。
税理士試験に受からない人の特徴③:試験の難易度を甘く見てしまう

必要な勉強量を正しく理解できていない
1科目あたり最低1,000時間の勉強が必要な試験です。
学習量を見誤ると、直前期に間に合いません。

以下はXで合格者に実施した、合格までの勉強時間の平均値。
アンケート結果の詳細は、各科目の記事で確認できます。
平均値なので、やってる人はもっと勉強しています。
独学のリスクや限界を把握していない
科目によっては独学が不可能というわけではありませんが、誤った理解に気づきにくい・情報が断片的などのデメリットがあります。
科目のクセや攻略法を理解していない
会計科目、税法科目はそれぞれ必要なスキルが異なります。
科目ごとの特性を理解しないと効率が下がります。
会計科目とは?
簿記論と財務諸表論の2科目。誰でも受験可能
税法科目とは?
法人税その他の9科目。受験資格が必要
税理士試験に受からない人の特徴④:計画性がなく時間管理に失敗している

学習スケジュールが立てられない・守れない
「今日は忙しいからやらない」が続くと、合格レベルとの差が一気に広がります。
やってる人は働きながらでも、毎日5・6時間は勉強しています。
仕事や家庭と両立できずペースが乱れる
社会人受験生は「安定した学習ペースを作れるか」が勝負です。

1日3時間以上の勉強時間が確保できないなら、以下の専門学校を選びましょう。
TAC・大原より網羅性は劣りますが、重要論点に絞った継続しやすいカリキュラムが特徴です。
直前期の追い込みが計画倒れになりやすい
直前期は焦りや不安で勉強が空回りしやすくなります。
「やることを絞る」がポイント。

「直前期にまとめてやる」では合格できません。
勝負は「直前期まで、どれだけ積み上げられたか」
重要論点から順番に潰していこう。
税理士試験に受からない人の特徴⑤:合格しづらい環境で勉強している

誘惑が多く集中を妨げる環境で勉強している
スマホ・ゲーム・テレビなど、集中を奪う要素が多いと学習効率が大きく低下します。

筆者は受験を始めてから10年間、テレビを持っていません。
ゲームも大好きでしたが、持つとやってしまうので全て処分しました。
家庭・仕事など外部要因で勉強効率が下がる
環境によって集中が途切れやすい人は、学習が安定しにくくなります。

勉強場所が固定されず習慣化しにくい
毎回場所を変えていると“勉強スイッチ”が入りにくく、学習が習慣になりづらいです。

基本は自宅。たまに気分転換でカフェがおすすめ。
税理士試験に受からない人にならないための解決策

専門学校に行き、アウトプット中心に切り替える
テキストより問題演習を優先するだけで、大きく学習効率が向上します。

感覚的にはインプット3、アウトプット7ぐらい。
モチベーションを仕組み化する
勉強時間を記録したり、小さな目標を設定すると継続しやすくなります。

勉強時間の管理には、Study plus・YPTを使おう。
現実的な勉強量と計画を立てる
1週間単位で計画を立て、無理なく続けられるペースを作りましょう。

働きながらでも最低、週25〜30時間は確保したい。
社会人でも続く時間管理ルールを導入する
朝の30分・昼休みの10分など、細切れ時間を武器にすることが大切です。

理論暗記は、スキマ時間を有効活用しよう。
合格しやすい勉強環境を整える
勉強机を固定する・スマホを別室に置くなど、小さな工夫で集中力は大幅に高まります。
税理士試験に受からない人の特徴と解決策まとめ

税理士試験は「才能」よりも、習慣・計画・環境・勉強方法が合否を分ける試験。
今回の5つの特徴に一つでも当てはまる場合は、そこを改善するだけで合格に大きく近づきます。
この5つを意識するだけで、合格可能性は確実に高まります。
「今の自分を知ること」が合格への第一歩。

今日から一つずつ改善していきましょう。
あわせて読みたい